| 池袋(いけぶくろ)/豊島区池袋2丁目 | |
 |
|
 |
 |
| ▲かつての三業地には、いまではアジア系外国人向けのアパートに変身 | |
| ●昭和30年代までのにぎやかな花街 今は寂れた商店街になっている三業通り商店街も昭和30年代までは,三味線の音色や芸者衆などが歩く賑やかな町でした。いわゆる三業地,花町だったのです。いまはマンションに建て替わっていますが,往時の面影を偲ばせるような雰囲気が残っています。三業地は花街、花柳界などの別名があります。いわゆる「料理屋」、「待合茶屋」、「芸者置屋」の三業態を指します。ほかに二業地なるものもあります。 ●江戸への野菜を出荷、名産に沢庵漬け 戦国時代は小田原北条氏の家臣・太田康資の所領でした。江戸時代は、幕府領および旗本領でもあります。村高は600石弱ですが、江戸へ出荷用の野菜を産出。名物の加工食品に沢庵漬けがあったとか。 |
|
| 感動度★ もう一度いきたい度★ 交通 JR山手線池袋駅から徒歩10分 |
|
| 西池袋(にしいけぶくろ)/豊島区西池袋2丁目 | |
 |
|
 |
 |
| ▲自由学園明日館(重要文化財) | ▲自由学園講堂(重要文化財) |
| ●ライト,遠藤新の作品が見られます 繁華街から迷路のような住宅地を抜けると,石畳みの似合う気品のある静かな町並みに抜けます。重要文化財の自由学園・明日館(みようにちかん)周辺です。池袋の雑踏とは無縁の世界で,静かな高級住宅地が広がっています。 帝国ホテルを設計したライトが教育者・羽仁夫妻の要望を受けて明日館を設計,大正10年(1921)に創立しました。さらに講堂を建築家・遠藤新が設計,その後の改築の指導にあたったのです。町並みの美しさに,週末は見学者が絶えないとか。 ●TVドラマ『相棒』にも登場! ちなみにドラマ『相棒』のシーズン18(2019〜20年)のオープニングの映像は「明日館」の内部での撮影で、毎回登場しました。 |
|
| 感動度★★ もう一度いきたい度★ 交通 JR山手線池袋駅から徒歩7分 |
|
| ○東池袋(ひがしいけぶくろ)/豊島区東池袋 | |
 |
|
| ▲美久仁小路/戦後すぐの“危険な飲み屋街”から見事に変わりました | |
 |
|
| ▲栄町通り/L字形の路地でやや雑然とした感じです | |
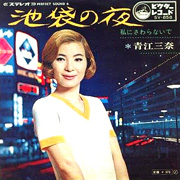 |
 |
| ▲青江三奈「池袋の夜」1969年7月に発売され、100万枚を超える空前のヒット曲となりました。 | ▲人生横丁の碑/人生横丁は平成20年7月に再開発で立ち退き。跡地にニッセイ池袋ビルが建つ。「池袋の夜」に歌詞として登場。 |
| ●駅を挟んで東西のヤミ市に1200軒!! 1945年4月、池袋周辺は第二次世界大戦の空襲で、ほとんどが焦土と化しました。その後、池袋駅周辺は焼け跡となり、ヤミ市が形成されていくのです。一説には駅を挟んで東西に、最も多いときで1200軒ものバラック建てや長屋式市場が広がっていたそうです。 ●焼け跡・ヤミ市が撤去後に4つの飲み屋街が誕生 1950年前後には経済復興が進み、戦災復興土地区画整理事業によってバラックや長屋はドンドン撤去されます。そのためヤミ市を営んでいた人たちは他の商店街などに移転します。また池袋に残留を希望する人たちは、東池袋1丁目に集まります。そして誕生したのが、「人生横丁」、「ひかり町通り」、「栄町通り」、「美久仁小路」の4つの飲み屋街。さらにその後の再開発で、「人生横丁」、「ひかり町通り」が消滅。現在、残っているのは「美久仁小路」、「栄町通り」の2箇所のみ。 ●“美久仁小路”と“人生横丁”は「池袋の夜」に登場 昭和歌謡の代表曲・青江三奈の『池袋の夜』(作詞・吉川静夫 作曲・渡久地政信)に、美久仁小路と人生横丁が登場します。100万枚を超えるヒット曲で、日本レコード大賞など数々の賞を獲得しました。 |
|
| 感動度★★ もう一度行きたい度★★ 交通 JR山手線池袋駅から徒歩15分 |
|
| 雑司が谷(ぞうしがや)/豊島区雑司が谷 | |
 |
|
 |
 |
| ▲雑司が谷旧宣教師館/明治40年築 | ▲鬼子母神堂/天正6年(1578)創建 |
 |
 |
| ▲雑二ストア/戦後にできたマーケット | ▲弦巻通り商店街の古民家群 |
 |
 |
| ▲都電荒川線の鬼子母神前駅 | ▲横丁には古民家がギッシリと詰まる |
 |
 |
| ▲大鳥神社/拝殿のきんちゃく袋型の賽銭箱がユニークです | ▲法明寺/梵鐘の模様に江戸時代の計算器が描かれています |
 |
 |
| ▲カレーライス(500円ランチ・木菟) | ▲羽二重団子セット(540円・大黒堂) |
| ●旧鎌倉街道が集落を縦断 地名の由来は諸説ありますが,鎌倉時代以後に起こった地名です。「雑司ヶ谷村」に統一されたのは,八代将軍徳川吉宗が鷹狩りのために立ち寄った折りに決めたとか。さて旧鎌倉街道が雑司が谷を横断しています。特に鬼子母神表参道から下る宿坂あたりは,街道の面影が偲ばれます。ところで鬼子母神は江戸時代から庶民の信仰を集めたところで,今でも参拝客が絶えません。 ●何度も訪ねても、その都度迷います しかし雑司ヶ谷全体は、迷路のような町で,実際に何度も迷いました。そしていたるところに古民家が見られるのです。庶民的でとても親しみを感じる町並みです。 |
|
| 感動度★ もう一度いきたい度★ 交通 地下鉄副都心線雑司が谷駅から徒歩10分 |
|
| ○目白(めじろ)/豊島区目白 | |
 |
|
 |
 |
| ▲學習院正門/明治41年(1908)築。国の登録有形文化財 | ▲目白警察署の紋章/警視庁管内唯一の旭日に桜の葉が囲む意匠 |
| ●四谷から移転してきた学習院がイメージアップ やはり、皇室とのつながりがあるというので、学習院大学の存在が大きいでしょう。明治期の陸軍軍人・乃木希典(のぎまれすけ)院長時代の明治41年に四谷から目白に移転してきました。学習院の移転で、その後の目白のイメージを高めたといっていいでしょう。また、かつて元総理大臣・田中角栄さんの住居のあった“目白御殿”も昭和政治の舞台にもなりました。 ●地名の由来はさまざまあっておもしろい とはいうものの、江戸時代は関口村という一寒村。ただ神田上水と江戸川の分水口にあたり“堰(せき)”があったからともいいます。また将軍の鷹狩りの場でもあったそうです。寛永年間(1624-44)、徳川3代将軍・家光が鷹狩りの折、目黒に対して目白と呼ぶべしといったという説があります。また白い名馬のが生まれたからという説、慈眼大師(天海)が江戸鎮護のため江戸四方に不動を造立し、その目を赤、黒、青、白の色にしたからという説などいろいろあります。ただJR目白駅は、明治18年に目白不動から名付けて開業したとか。豊島区内では最古の駅でもあります。 ●ガラス戸やガラス窓がユニークです JR目白駅を出て右へ曲がり、そのまま目白通りを行きますと、学習院や川村学園など、文京地帯となります。そして目白警察署の先に古民家がポツンと残されています。ごく平凡な木造2階家で、戦後の建物。ガラス戸、ガラス窓が異彩を放っています。 |
|
| 感動度★ もう一度行きたい度★ 交通 JR山手線目白駅から徒歩5分 |
|











