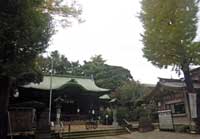| ●世田谷(せたがや)/世田谷区世田谷1丁目 | |
 |
|
 |
 |
| ▲世田谷代官屋敷/大場氏は井伊家世田谷領の代官職。江戸中期の茅葺き屋根で国の重要文化財に指定。子孫は世田谷区長にもなりました | |
 |
 |
| ▲中華そば(500円・味の大ちゃん) | ▲ボロ市そば(750円・いづみ家) |
 |
 |
| ▲ラーメン(500円・来々軒) | ▲ラーメン(780円・品芳斎) |
 |
 |
| ▲正油ラーメン(500円・美幌ラーメン) | ▲ラーメン(500円・あづま) |
 |
 |
| ▲カレーライス(500円・やまぐち) | ▲薬きょう(1個50円) |
| ●大山道沿いの代官屋敷 江戸中期以来,彦根藩領であったのですが,世田谷20カ村の代官を世襲したのが大場家で,大場代官屋敷ともいわれています。大名領の代官屋敷としては都内ではココだけです。 表門(写真)は茅葺きの長屋門です。主屋も茅葺き屋根,寄せ棟造りで何度か改修・増築されたようです。 ●毎年12月と1月にボロ市が開催 現在の世田谷通りから一本南側に江戸と小田原を結ぶ大山道があります。かつて大山参拝でにぎわった街道ですが,いまは毎年2回,ぼろ市で賑わっています。なお上記のメニューはボロ市開催時の価格。 |
|
| 感動度★ もう一度いきたい度★ 交通 東急世田谷線上町駅から徒歩5分 |
|
| ●豪徳寺(ごうとくじ)/世田谷区豪徳寺 | |
 |
|
 |
 |
| ▲豪徳寺/世田谷城主吉良氏が建立 | ▲井伊家2代藩主・井伊直孝の墓所 |
 |
 |
| ▲世田谷城址公園/吉良氏の居城 | ▲古道沿いに板張りの民家が点在 |
| ●古道・瀧坂道が世田谷区を縦断 区民にもあまり知られていない瀧坂道(たきさかみち)が世田谷を縦断しています。江戸時代の初期,甲州街道が開設される以前,江戸(青山)と府中を結ぶ重要な街道でした。この街道,豪徳寺界隈で90度に曲がったり,S字カーブを繰り返します。中世になって吉良氏が居館をこの地に設けましたが,高台や湿地帯を利用しながら防衛目的で整備されたとか。 ●世田谷区の風景資産 いま歩いてみますと,大部分が現代住宅に変わっています。ときおり茅葺きをトタンで葺き替えた町家も見られます。世田谷区が風景資産として紹介しています。 |
|
| 感動度★ もう一度いきたい度★ 交通 東急世田谷線宮の坂駅から徒歩5分 |
|
| ●池尻(いけじり)/世田谷区池尻 |
 |
| ●村高はわずかに45石! 中世から重要な街道でしたが,江戸時代に入るや,大山詣でアッというまに賑わいました。江戸時代は元禄年間(1688-1704)から幕府領。村高は45石前後とわずかです。土質が悪いことと、目黒川の氾濫が原因とか。 ●大山道沿いに旧家 で、いま歩きますと,わずかに古民家や旧家が残されていますが,過日の古街道の面影はありません。「大山道」の石碑や貼り紙が見られる程度。一部の古文書には「池ノ尻村」と記されているそうです。地名の由来はよくわかっていません。一説には池上(いけのうえ)に対する意味があるとか。 |
| 感動度★ もう一度いきたい度★ 交通 東急田園都市線池尻大橋駅から徒歩5分 |
| ●三宿(みしゅく)/世田谷区三宿 | |
 |
|
 |
 |
| ▲萩原家住宅/国の登録文化財 | ▲廃屋(?)も見られます |
| ●建築家・遠藤新の作品が文化財に 江戸時代は大山道沿いの集落として発展。地名の由来は上、中、下の三宿があったからというが定かではありません。関東大震災後,三軒茶屋周辺は郊外住宅地として開発されました。萩原家住宅はその初期の時代の建築で,しかも遠藤新(えんどうあらた)の作品として貴重な存在です。周囲は現代住宅がギッシリ詰まっており,ときおり古民家を散見。 ●江戸期はやせ細った土地 江戸時代は寛永2年(1625)より旗本・ 竹尾四郎兵衛の知行。元禄8年(1695)から幕府領となります。村高は80石弱とわずか。この地は黒土に赤土が混ざった痩せていました。米わわずかで、雑穀、蔬菜を生産していました。 |
|
| 感動度★ もう一度いきたい度★ 交通 東急田園都市線三軒茶屋駅から徒歩10分 |
|
| ●太子堂(たいしどう)/世田谷区太子堂 |
 |
| ●源義家が奥州征伐の途上、この地で酒宴を開く 戦国時代、源義家が奥州征伐の途上、一行らを休めて酒宴を開きました。そのとき酒宴に使用した土器を埋めたのが土器塚であるという伝説があります。この土器塚は旧代田村との境界にあるそうです。 ●住宅密集地帯でも古民家も多く残る 町名の語源は,法明院円泉寺の境内に長さ1尺1寸の弘法大師作の聖徳太子像をまつる太子堂があるのにちなんだとか。江戸時代は太子堂村で,範囲は変わっても現代まで町名に変化はありません。住宅の密集地帯ですが,古民家も散見されます。 |
| 感動度★ もう一度いきたい度★ 交通 東急田園都市線三軒茶屋駅から徒歩7分 |
| ●若林(わかばやし)/世田谷区若林 | |
 |
|
 |
 |
| ▲松下村塾(模造)/松陰神社境内にあり、土日祝日のみ雨戸を開けます | ▲東京聖十字教会/「かまぼこ型合掌造」と称される・昭和36年築 |
| ●歴史ある若林 若林という地名は室町時代からあったと思われ、『私案抄』(深大寺僧侶・長弁の文集)にも登場します。江戸時代は荏原郡若林村。村高は120石余と地味はやせていたようです。しかし交通は意外に便利で、甲州街道瀧坂道が村の中央を、矢倉沢往還(大山道)が村の南端を東西に走っていました。 ●吉田松陰の遺骨を改葬して松陰神社へ 幕末期、吉田松陰らの遺体が回向院(荒川区)で埋葬され、のちに改葬されて遺骨を松陰神社に移されました。明治15年(1882)のことです。なお萩・松陰神社へは遺髪が送られました。 ●古い住宅はわずかとなりました 若林は住宅の密集地域でもあります。一部は迷路となり、タクシーの運転手でも迷うとか。しかしほとんどが現代住宅で、古い住宅はわずかとなりました。なお東京聖十字教会の設計はアントニン・レイモンドで、内部の長椅子もレイモンドのデザインです。 |
|
| 感動度★ もう一度行きたい度★ 交通 東急世田谷線松陰神社前駅から徒歩6分 |
|
| ●三軒茶屋(さんげんぢゃや)/世田谷区三軒茶屋 | |
 |
|
 |
 |
| ▲大半はスナック,バー,食堂などの飲食店が中心です | ▲アーケードのあるエコー仲見世商店街には21店舗 |
 |
 |
| ▲明太カルボうどん(380円・楽釜製麺所) | ▲ゆず鶏ほうれんそうそば400円富士そば |
| ●戦後の闇市を彷彿させる 国道246号と世田谷通りに挟まれた三角地帯に,再開発から取り残された町があります。土地等の権利関係の複雑さから,手つかずの状態になっているのです。町並みは大きく分けて,雑貨店や呉服店などのあるアーケード街とバー,スナック,食堂などの飲食店街の二つに分かれます。最近は「三茶三角博覧会」と名乗るイベントを開催。 ●3軒の茶屋がありました 江戸時代,大山へ向かう参詣道の分かれ道に3軒の茶屋があったことが地名の由来。今,商店街は再開発派と現状維持派に分かれているとか。 |
|
| 感動度★★ もう一度いきたい度★ 交通 東急田園都市線三軒茶屋駅からすぐ |
|
| ●用賀(ようが)/世田谷区用賀 | |
 |
|
 |
 |
| ▲無量寺/約400年前に開基 | ▲真福寺/北条氏の家臣が開基 |
| ●新旧の大山道の合流地 江戸から相模に向かう新旧の大山道(矢倉沢往還)はこの地で合流します。街道沿いには,醤油屋,油屋,紺屋,酒屋,料理屋,後に旅籠もできます。江戸後期になると相模から江戸への物資の輸送,人々の往来も盛んになります。特に大山参拝の道筋にあたり,用賀村は大変賑わったそうです。 ●地名の由来は仏典語からでた言葉 世田谷の郷土史家・鈴木堅次郎氏は用賀は仏典語から出た言葉で,瑜伽(梵語・ユガと読むが、原語はヨーガ)が,わかりやすい用賀になったと指摘。いまでは定説となっているとか。 |
|
| 感動度★ もう一度いきたい度★ 交通 東急田園都市線用賀駅から徒歩5分 |
|
| ●岡本(おかもと)/世田谷区岡本 | |
 |
|
 |
 |
| ▲武家屋敷門/江戸中期の建物 | ▲岡本民家園/旧長崎家住宅 |
 |
 |
| ▲静嘉堂文庫/大正2年(1913)築 | ▲旧小坂家住宅/昭和12年築 |
| ●政財界人の別邸が並ぶ 江戸時代は慶安4年(1651)までは幕府領,以後彦根藩井伊家領。江戸時代から風光明媚な景勝地でした。明治時代後期から昭和初期にかけて,政財界人などの別邸が建てられました。 ●“東京の軽井沢”の異名で分譲地も 昭和初期の新聞広告を見ますと,“東京の軽井沢”の異名で分譲も始まっています。というのも国分寺崖線が通っているため,台地から多摩川や富士山が遠望できたからです。今は近代木造住宅も10棟未満に落ち込んでおり,古民家も皆無に近いですが,文化財が点在しており,年中ハイカーが絶えません。 |
|
| 感動度★ もう一度いきたい度★ 交通 東急二子玉川駅から生育医療研究センター行きバスで静嘉堂文庫下車すぐ |
|
| ●喜多見(きたみ)/世田谷区喜多見 | |
 |
|
 |
 |
| ▲氷川神社/区内で最古の石鳥居 | ▲次代夫堀公園民家園/文化財多数 |
| ●犬公方・綱吉の時代に1万3000余匹の犬を飼う 江戸時代,世田谷城主・吉良氏の家臣であった喜多見氏は文禄元年(1592),喜多見村の旧領地を与えられ,2万石の大名までになります。その後,犬公方として知られる徳川綱吉への背信行為をしたとして、喜多見氏はお家断絶。その後幕府領となり、中野村(中野区)などと同じように犬小屋が設置されます。最大1万3千余匹が飼育されたそうです。 ●土蔵など少し残る いまは住宅地として発展しており,往時の面影は全く見られません。歩きますと土蔵や板塀のある町家は少し見られます。 |
|
| 感動度★ もう一度いきたい度★ 交通 小田急線喜多見駅から徒歩20分 |
|
| ●上野毛(かみのげ)/上野毛3丁目 | |
 |
|
 |
 |
| ▲日本の古美術が中心の五島美術館 | ▲不老門/不老長寿を願う意味を持つ |
| ●国分寺崖線に連なる高級住宅 「ノゲ」は古文で崖という意味だそうで,上野毛は「崖の上」になります。このあたりは国分寺崖線(がいせん)といいい,立川市,国分寺市から崖が連なるところです。多摩川が10万年以上かけて武蔵野台地を削り取ってできた崖なのです。そんな所を世田谷区は「おもいはせの路」という散歩道を設定しました。 ●季節やときの流れを捉える「おもいはせの路」 おもいはせの路は、古代から現代までさまざまな顔が見える散歩道です。文化財を多数有する九品仏浄真寺からはじまり、途中は23区内随一の渓谷・等々力渓谷や上野毛自然公園、最後はオシャレな町・二子玉川までの約6.7kmのコースです。 ●国宝『源氏物語絵巻』所蔵の五島美術館 東急の創始者・五島一族の邸宅のあるところです。周辺は超豪邸が並びます。また五島慶太氏が集めた美術品は第一級品で,国宝,重文クラスが五島美術館に多数収納。特に最高傑作といわれる『源氏物語絵巻』(鈴虫一、鈴虫二、夕霧、御法)を所蔵。いずれも国宝で、定期的に公開されますが、公開日は見学者で長蛇の列となります。 |
|
| 感動度★★ もう一度いきたい度★★ 交通 東急大井町線上野毛駅から徒歩8分 |
|